「交流分析」とはどのような事を可能にする心理学なのか。勉強するとどう役に立つのでしょうか。
交流分析の理論と技法を日常の診療・治療に実際に役立てて効果を上げておられる中部労災病院心療内科の芦原睦先生に、連載の第5回目は、「脚本分析」についてお書きいただきました。
。
交流パターン(やりとり)分析
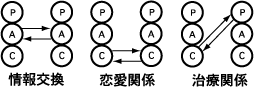
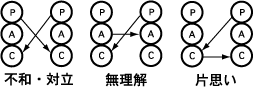
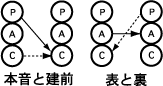
対人関係の交流パターンの例を図に示しました。交流パターンは図の上から
1)相補交流
2)交差交流
3)裏面交流
の3つ分けることができます。
図の上段に示した相補交流では会話のベクトルは並行で交わることがありません。
このような交流が行われている限り会話はスムーズに流れ、感情的対立は起こりません。
しかし図の中段に示した交差交流の例ですと会話のベクトルは交差し、双方に嫌な感情を残します。
図の下段の裏面交流はやや複雑ですが表面的にかわされる会話とその底にある真のメッセージが異なる場合です。要するにホンネを隠してタテマエで話しているようなものです。
これらの交流パターンの特徴を頭に入れておきますと、対人関係のトラブルがぐっと減るものです。
つまり話し相手の会話が、相手のP、A、Cのいずれから発せられたもので、自分はどう受けるのが適切かという具合にです。相手があまり感情的になり過ぎていてPやCからしかメッセージが来ない場合、あえて自分のAから交差交流をして、相手のAを誘発するというカウンセリングで用いられる方法もあります。
ゲーム分析
TAでは対人関係において繰り返し行われる非生産的な行動をゲームと呼びました。ゲームにおいては会話がかわされる両者共に不快な感情が残るのが特徴です。いつも夫婦喧嘩ばかりしている夫婦を、皮肉な意味でゲームと呼んでいると思えばわかりやすいでしょう。ゲームを発見し、そのゲームを治療の過程でとりあげるのが、ゲーム分析です。
新しい提案に対し、いつも「ハイ、でも」と言って拒絶を続ける「ハイ、でも」のゲームや、何でも他人のせいにしてしまう「あなたのせいでこんなになったんだ」というゲームなど、興味深いネーミングのものがあります。ゲームに関しては、是非参考図書を御一読されることをお勧めします。
第1回-1:交流分析って何?
第1回-2:交流分析(TA)の哲学
第2回-1:3つの欲求理論と4つの分析理論
第2回-2:ストローク
第2回-3:時間の構造化
第3回-1:構造分析
第3回-2:自己成長エゴグラム
第4回:基本的対人関係の構え
第5回-1:交流パターン(やりとり)・ゲーム分析
第5回-2:脚本分析
|

